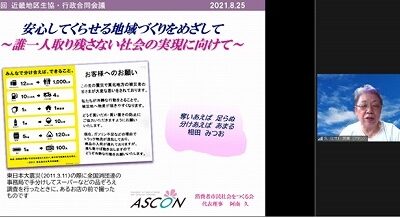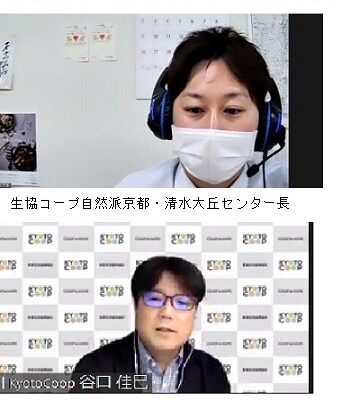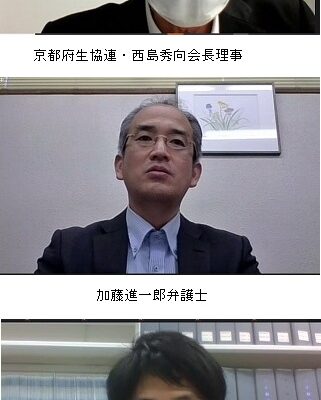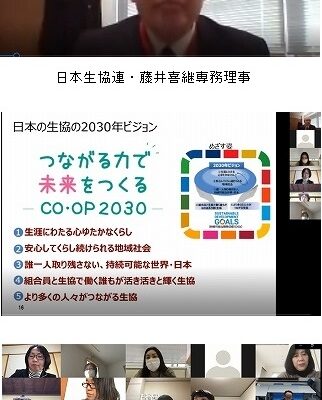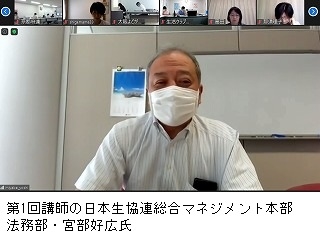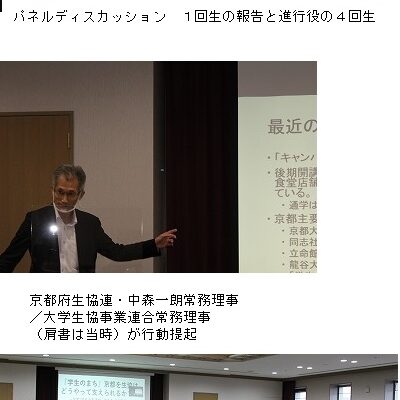2021年8月25日(水)、和歌山市アバローム紀の国とオンラインで開催し、42人が参加しました。主催は近畿地区生協府県連協議会。テーマは「安心してくらせる地域づくりをめざして~誰一人取り残さない社会の実現にむけて」。
はじめに近畿地区生協府県連協議会代表・兵庫県生協連・岩山利久会長理事と、和歌山県環境生活部・生駒亨部長よりあいさつがありました。次に厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室・内山徹室長よりあいさつと報告、日本生協連執行役員・伊藤治郎渉外広報本部長より「持続可能な社会の実現を目指した全国の生協の社会的取り組み」について報告がありました。
一般社団法人消費者市民社会をつくる会・阿南久代表理事より「消費者行政と生協への期待~安心してくらせる地域づくりをめざして~」をテーマに特別講演がありました。
活動事例として和歌山県橋本市総務部市民課・大岡久子課長より「消費者行政によるエシカル消費推進啓発事業」、JA大阪中央会総務企画部・久保裕章次長より「協同組合・非営利セクター連携組織設立のとりくみ」、福井県民生協・中川政弘常勤理事より「福井県民生協の協同組合間連携の取り組み」、特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)・元山鉄朗事務局長より「特定非営利活動法人KC’s の活動」についての報告があり、和歌山県生協連・久保田泰造会長理事より閉会のあいさつがありました。